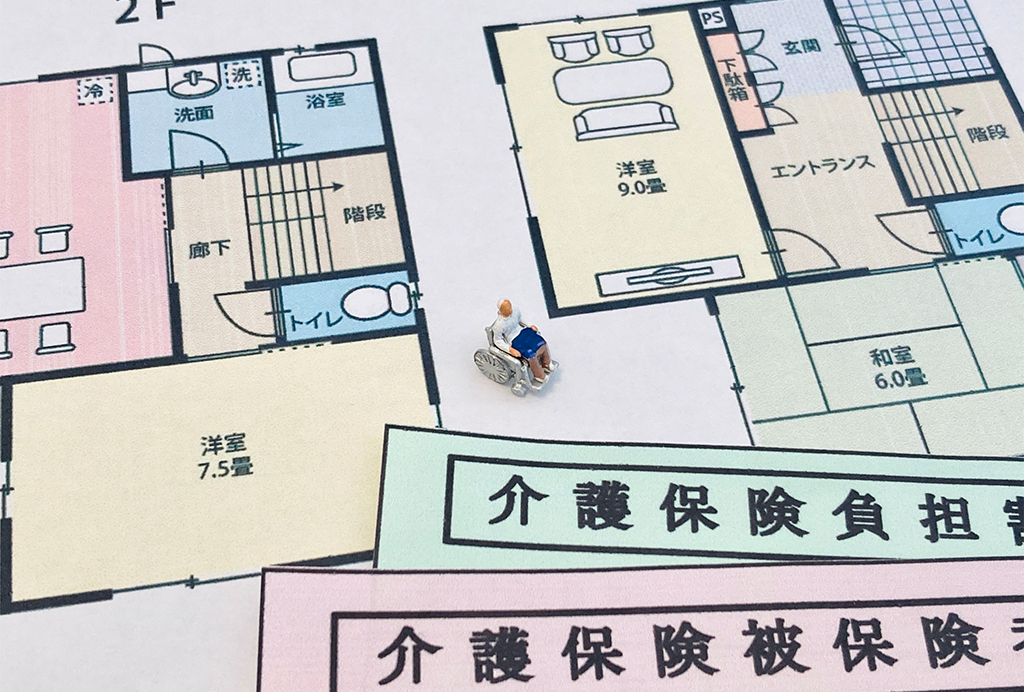介護・福祉制度について

公的介護保険について
公的介護保険制度は介護が必要とされる人を社会全体で支える仕組みです。
40歳以上の方は全員が加入対象となり、介護保険料を納めます。
40歳~64歳と65歳以上では、介護保険料や納付方法などが変わるため、切り替わる時期は注意しなければなりません。
●サービスを受けられる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支障が必要な状態(要介護状態)になった場合にサービスが受けられます。
病気やケガなど介護が必要になった原因にかかわらず介護保険が受けられます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
(医療保険に加入している方)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
事故や他の病気など特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象となりません。
特定疾病とは
- ●筋萎縮性側索硬化症(ALS) ●後縦靱帯硬化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症
- ●他系統萎縮症(シャイ・ドレガー症候群)
- ●初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症(ウェルナー症候群等)
- ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- ●脳血管疾患 ●パーキンソン病 ●閉塞性動脈硬化症
- ●慢性関節リウマチ ●慢性閉塞性肺疾患 ●末期がん
- ●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
実際にサービスを受けるには?

実際にサービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
介護保険利用手続きの流れ
サービス利用までの流れをご確認いただけます。

①要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

②認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

③審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

④認 定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

●ケアプランとは?
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
【要介護1~5と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。
詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。

⑥介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
介護認定の方の状態区分について
審査結果により、以下のいずれかの状態区分に認定されます。(要介護・要支援度(要支援1~要介護5の7段階))
※要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。
| 要支援1 | ・日常生活を送るうえで必要な行動の一部に、手助けが必要な状態。 ※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど ・改善したり回復したりする可能性が高い。 |
|---|---|
| サービス利用額の上限 支給限度額(月額)4,970単位 |
|
| 要支援2 | ・日常生活を送るうえで必要な行動に、部分的な手助けが必要な状態。 ※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど ・要介護状態になる可能性があるが、改善したり回復したりする可能性が見込まれる。 |
| サービス利用額の上限 支給限度額(月額)10,400単位 |
| 要介護1 | ・日常生活を送るうえで必要な掃除や着替えなど、全般的に介助が必要な状態。 排泄や食事などの基本的な動作は、ほぼ一人で行うことができる。 |
|---|---|
| サービス利用額の上限 支給限度額(月額)16,580単位 |
|
| 要介護2 | ・身の回りの世話の全般、立ち上がり、歩行、移動の動作などに介助が必要。 排泄や食事などの動作に対して、見守りや手助けが必要なときがある。 ・認知症の場合、物事の理解が難しくなる状態。 |
| サービス利用額の上限 支給限度額(月額)19,480単位 |
|
| 要介護3 | ・日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。 身の回りの世話が必要で、立ち上がり、歩行、移動などがほとんど自分でできない。 ・排泄や食事がほぼ自分でできない状態。認知症による判断力の低下がみられる。 |
| サービス利用額の上限 支給限度額(月額)26,750単位 |
|
| 要介護4 | ・介護なしで日常生活を送ることが困難な状態。 身の回りの世話が必要で、立ち上がり、歩行、排泄などが自分でできない。 ・判断能力の低下がみられ認知症の周辺症状が増えている。 |
| サービス利用額の上限 支給限度額(月額)30,600単位 |
|
| 要介護5 | ・ほぼ寝たきりの状態で、介護なしでは日常生活を送ることができない。 ・判断能力の低下がみられ、認知症の周辺症状が多い。 |
| サービス利用額の上限 支給限度額(月額)35,830単位 |
介護保険における福祉用具のレンタルサービスのご案内
レンタル期間、及び期間の延長について
レンタル最短契約期間は1か月です。
レンタル期間の延長については、解約のお申し出がない場合は1か月単位で自動継続となります。
レンタルサービスご利用の終了日は、ご利用者様(ご家族様)からご連絡いただいた日になります。
終了の際は直ちにご連絡ください
レンタルサービス料金の計算方法について
| ◆レンタル開始月の場合 | ||
|---|---|---|
| レンタル契約開始日 | 1~15日の場合 | 1ヶ月分 |
| 16~末日の場合 | 1ヶ月分 | |
| ◆レンタル終了月の場合 | ||
| レンタル契約開始日 | 1~15日の場合 | 半月分 |
| 16~末日の場合 | 1ヶ月分 | |
レンタルサービス料金のお支払い方法、及びお支払い期日について
原則として、納品時に当月のレンタルサービス料金をお支払いください。
翌月以降のお支払い方法及びお支払い期日につきましては、レンタル規約に基づいてお支払いいただきます。
サービスをご利用いただいているにも関わらず、お支払いがない場合には、商品を引き上げさせていただく場合があります。

介護保険における特定福祉用具の販売
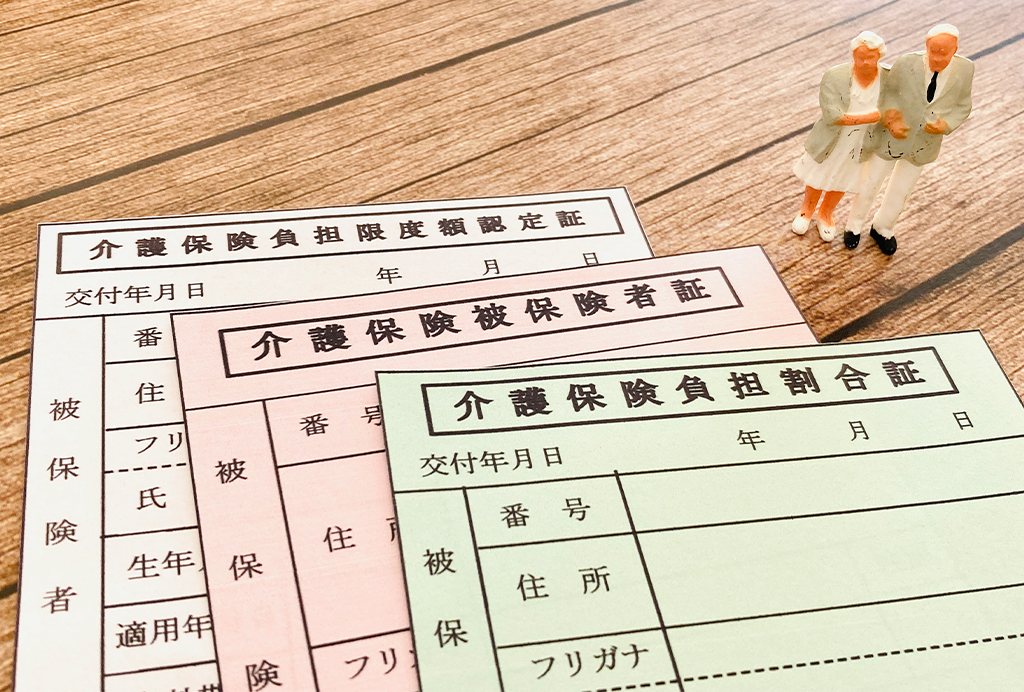
●支給対象・・・要支援〜要介護5と認定された方。
●利用限度額・・・毎年4月から1年間で10万円(税込)
●異なる福祉用具を組み合わせて購入できます。
(同一種目同士の組み合わせは不可)
●ご利用者負担額は、1〜3割負担となります。
●お支払い方法は償還払いまたは、受領委任払いです。(要確認)
介護保険による住宅改修サービス
●支給対象・・・要支援〜要介護5と認定された方で、在宅で生活し住宅改修が必要とされる方。(事前申請)
●利用限度額・・・現住居につき20万円(限度)。
要介護度が3段階以上進んだ場合、または転居した場合に再度20万円限度で利用できます。
●ご利用者負担額は、1〜3割負担となります。
●お支払い方法は償還払いまたは、受領委任払いです。(要確認)
介護保険の改修費支給対象の住宅改修の項目
・手すりの取り付け
・段差の解消
・床材の変更
・引き戸等への扉の取替え
・便座の取替え・位置変更
・上記の住宅改修に付帯する工事